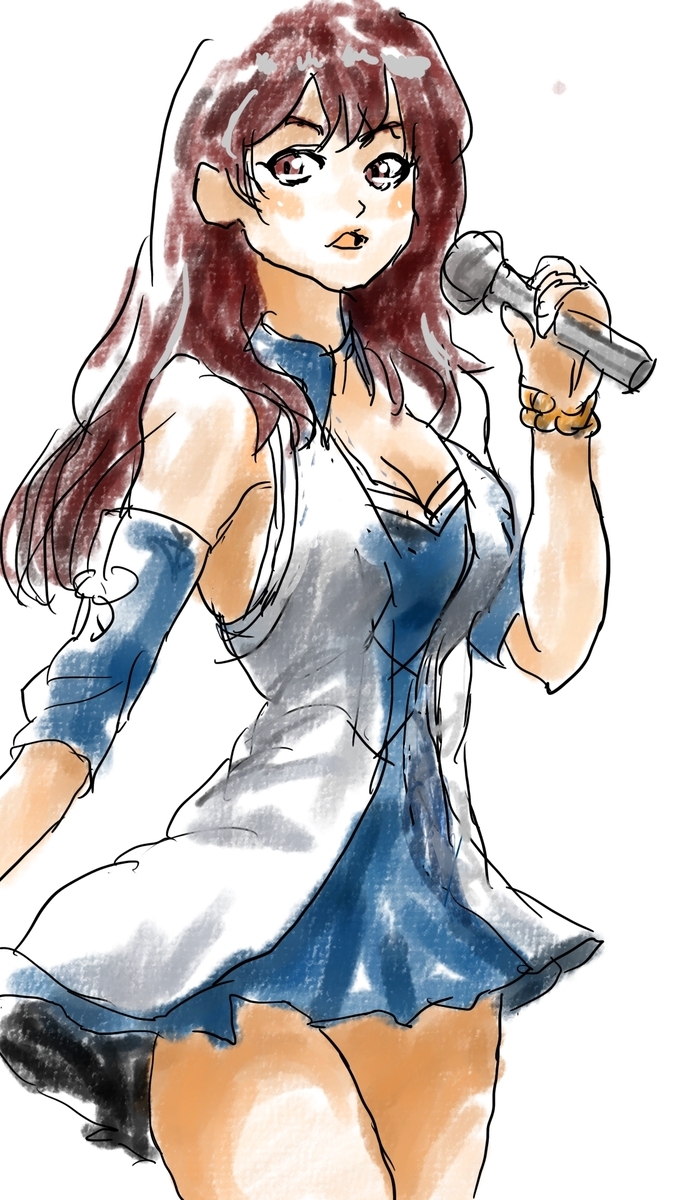
ガラクはある日突然、自分が殺し屋と軍人の娘であることを知る。そして自らの身体にも、戦いのサラブレッドとしての血が流れていた。両親の師匠にして親代わりでもあるレックスの紹介で、民間軍事会社ガルーサ社で軍人としての第一歩を踏み出す。そこで待っていたのは、死んだと言われていた母ゼツだった。最新鋭の戦闘機でやってきた母に連れられて、中東のアルバラ共和国パルミラ基地を目指す。基地を目前にしてパルミラの手練れに囲まれるが、父ラルフと仲間の機転で切り抜けることができた。懐の深い司令官クリスは、ゼツとガラク、ラルフに給油を許した。山岳基地パルミラに降り立ったガラクとゼツ。突然襲ってきたスパイ狩りを退けた後、彼女たちを待ち受けていたのは頼りになる、あの老人だった。
「しかし、お前さんも損な役回りだな」
白髪頭を掻きむしりながら、ハーティ・ホイルが人懐っこい笑みを浮かべた。
「ナセルとは、殺し合う理由がない。
成り行きで敵同士になってしまっただけさ ───」
窓の外には黒くそそり立つ山が連なり、先ほどから降り始めたにわか雨が視界を濡らしていた。
「ほれ、砂漠も悲しいとさ。
天気ってやつは、意外と人間の心を写しているものさ」
「確かに、今日は湿っぽくなる気分かも知れないな」
計器の上に手を突いて、クリスは黒い雲に覆われた空をぼんやりと見上げる。
灼熱の砂が広がる平地と、荒々しく尖った岩肌は、人を寄せ付けない|過酷《かこく》なアルバラという風土がもたらす風景である。
そして泥沼化する紛争が、大きくなり続けて今に至る。
戦争が起これば武器を売り込みに商人がやって来て、敵味方関係なく金さえ払えば武器を売る。
つまり、金が尽きた方が負けるのが、現代の戦争である。
個人の信念よりも、最新の武器に、とりわけこの地では戦闘機を手に入れなくてはならない。
その戦闘機を手足のように操るパイロットも|勿論《もちろん》である。
「政府軍も、反政府軍も、ドッグファイトにおいては外人部隊の敵ではない。
ほとんど七面鳥撃ちだ」
「そいつは、死線をくぐったエトランゼの連中が特別なのさ」
頭を抱えてクリスはハーティに背を向けた。
「俺は、時々恐ろしくなる。
自分が、ただの|殺戮《さつりく》をしているのではないかと ───」
「ワシも同じさ。
武器を売っていれば、戦争を大きくしているようなものだ。
そろそろ潮時だと思っている。
お前さんのように、自分の行く末を本気で考える人間が近頃増えてきた。
お陰で、ワシも自己嫌悪に駆られるようになってな」
ツカツカとドアに向かって歩いて行くと、老人は背中を向けたまま言った。
「国を捨て、信念を捨て、家族を捨て、人生を捨て、未来を捨て、魂を捨てても残った物がある」
「それは、何だ ───」
「『男の尊厳』だよ」
ホーネットのダークグレーの翼が、地上の目標を捉えようとしていた。
山岳地帯へギリギリの高度で侵入すると、地上からは視認しづらくなる。
平地へ出る瞬間、地対空ミサイルが雨あられと襲いかかってきた。
センサーが反応し、けたたましい音と共に視界が赤く囲われる。
機体をロールさせながら、真っ直ぐに斬り込む。
「ビービーうるせえ。
ミサイルが来てるのは分かってるんだ。
|喚《わめ》くんじゃねえ」
|操縦桿《そうじゅうかん》をわずかに引き、爆弾を投下すると同時に戦車へ20ミリバルカン砲の雨を浴びせる。
「戦車がウジャウジャ居やがる。
もう一回積んで出直すぞ」
「おい、ラルフ。
あまり入れ込むなよ。
ミッションはほぼ達成した」
上空を旋回して、敵戦闘機を|威嚇《いかく》していたホワイトの声だった。
装甲車の群れを攻撃し、正規軍の補給路を断つ目的はほぼ|完遂《かんすい》していた。
後方の砂漠から、石油が燃える黒い煙を確認すると、ふうと一つ息をついた。
「それもそうだな。
全機、帰投する。
燃料が少ない者から先に行け」
ラルフは2機を引きつれて、また低空飛行でアル・サドンを目指した。
陽が沈みかけ、雨雲が砂漠に暗い影を落とす。
「荒れそうだ。
雲の上に出ろ」
ホワイトの指示に従って、3機は暗い塊を突き抜けていく。
真っ暗な視界から高度計に視線を移すと、3000メートル程の高さで雲の上に出た。
ウソのようにカラッと陽が差して沈む太陽を認めた。
「また雨か。
ラルフが来てから、増えた気がするな」
ふと、ラルフの脳裏に娘の顔が浮かんだ。
そして胸騒ぎが、呼吸を苦しくさせた。
「中東の先輩として言わせてもらうが、感情的になるなよ。
任務を冷静に遂行していれば、生き残って地上へ降りられる。
お前には家族がいるのだから、無駄死にはするな」
ホワイトの声は、珍しくトーンダウンしていた。
「ホワイト、お前こそ他人の心配とは、ヤキが回ったんじゃないのか」
4機は横に並び、渡り鳥のように上になり、下になり、風に身を任せるように揺らいでバーナーの尾を引いて行ったのだった。
ライトニングⅡを納めたハンガーに戻ったゼツは、木箱の山の隅に腰を下ろした。
後ろに束ねた髪をほぐし、もう一度縛り直すと、ガラクの方に視線を向けた。
「どうしたんだい。
そう気を張っていちゃあ、いざって時息切れするぞ」
「お母さんこそ敵地の真ん中で、髪を結び直してる場合なの」
油断なく倉庫の隅々まで見回し、突っ立っている娘の姿が|可笑《おか》しくなってゼツは吹き出した。
「あははは、違いないな。
お前の方が正しいよ、きっと」
すっくと立ち上がると、一緒になってキョロキョロ見回して、また笑い出す。
「私のこと、バカにしてるわね」
|頬《ほお》を少し|膨《ふく》らませて、口を尖らせた。
「恐怖も緊張も、生き残るために必要な感情だよ。
私だって、家でのんびりしているときと一緒じゃないさ」
脇に仕込んでいたベレッタを抜き、何かを確かめるように眺めたまま母の目尻がわずかに引き|攣《つ》るのを認めた。
「何」
背後で何かが動いた。
全身の毛穴が開き、髪がふわりと浮く感覚と、足元がどっしり地面に食いつく感覚。
ファリーゼで銃撃戦を初めて見て、死を直感した時と同じだった。
ゆっくりと身体を|捻《ひね》り、視界に捉えたのは美しいブロンドの長髪でスラリとしたファッションモデルのような若い娘の姿だった。
「あんたたちは、正義の女神アストライアか」
銃をホルスターに収め、足で地面を|擦《す》るように、滑らかな足取りで近づいてくる。
「あ ───」
彼女の挙動には無駄がなかった。
|隙《すき》のない身体には、心を素手で|掴《つか》まれるような重い|威厳《いげん》が備わっていた。
「わ、私はガラクよ。
母のゼツは強いけど、私はからきしでね」
「私の名前はナット・ジェナー。
この状況では、こっちが死に|体《たい》なんだけどな ───」
喋りながら徐々に口元が緩み、ついに腹を抱えて笑い始めた。
「ガラク、私はちょいと大人の用事をしてくるから遊んでおいで」
優しく娘を|愛《いと》おしむような|双眸《そうぼう》に、ジェナーは軽く会釈してガラクを引っ張って奥へと消えていった。
アルバラ共和国空軍基地である、アル・サドンは元々中立的な立場だったが戦況が|芳《かんば》しくない反政府軍を支援する外人部隊になった。
総司令官のナセルは政府軍外人部隊にいるクリスと旧知の中であり、戦友でもある。
物静かで闘志を内に秘めるタイプだが、愛機クフィルのコックピットに収まれば、軍神マルスと見紛うばかりの勇敢さと、虎をも射殺す|獰猛《どうもう》さを|露《あら》わにする。
「ホワイト、塩取ってくれんか」
「ほい、投げますよ」
ほぼ直線を描いて飛んだ味塩が、ひょいと上げた右手に乾いた音と共に収まった。
「ほれ、お前も使え、アリー」
戦闘機乗りとして、超一流の腕前を誇る3人は、何度も共に死線をくぐった仲間と言って良かった。
簡易食堂のトレーを並べて ゆで卵 とカレー、サラダとスープを口に運ぶ姿に階級差は感じられない。
「最近のラルフの活躍は、神がかっているな」
他人事のように、アリーが言った。
「この前は『戦車がウジャウジャいやがるぜ』なんて言って、もう一度出ようとしたが基地に帰らせたんだ」
「ほう、娘には会えたのだろう」
「そのようですが、妙に張り切っていて少々心配です」
スプーンを止めたナセルは、思案顔で遠くの壁を眺めていた。
「彼は、根っからの軍人ではないと思います」
ホワイトも手を止めた。
「と言うと ───」
「我々よりも、遥か未来を|見据《みす》えて生きている。
そんな感じがするのです」
カチャリと食器を乗せたトレーを持ち上げたアリーは、ホワイトの言葉を聞いて表情を引きしめた。
「我々に、未来はあると思うか」
「いいえ、未来を捨てた人間が叫び、踊るために集まるのが戦場というものです」
「違いないな。
作戦会議の前に、奴のホーネットのガンカメラを確認しただろう。
どう思った」
「正直、敵には回したくないですね。
挙動に理解不能なニュアンスを織り交ぜて、最短距離で敵に向かい正確無比の攻撃をしていました」
「アル・サドンの元ナンバーワンであるアリーも舌を巻くか ───」
そんな話をしながら、3人は管制塔へと引き上げて行った。
敵の基地に潜入しているというのに、娘は若い友人でも見つけたかのように共に笑った。
そしてゼツ自身も、自分に向けた殺気がほとんど感じられないことに違和感を感じていた。
「アル・サドンのゼツ・ノエル・オリベールです」
管制塔まで来るようにと、整備兵に言われてやって来たが、ドアは開け放たれて、廊下をジョギングしていた兵士も|一瞥《いちべつ》しただけで走り去って行った。
レーダーを見ていたクリスが振り向くと、握手を求めてきた。
「司令官のクリスティ・ドゥイ・ブロトン大佐だ。
あなたに撃たれたファリド・ハッサンは、故郷のアラブに送ったよ。
鮮やかな手際だな。
正規軍には『スパイなど、くそくらえだ』と打っておいたぞ」
両手を小さく上げて、降参した、というポーズを取りながら言った。
「戦闘機ではお宅の若い兵士に撃ち落とされそうになったがね。
地上に降りれば私の土俵だよ」
「ガルーサ社の大佐だそうだな。
うちにも何人か来ている。
まあ、外人部隊の人間関係は複雑だ」
外に目をやると、陽は沈み、雨粒が窓ガラスを伝って流れていた。
「ナセル指令から、クリス指令によろしくと言われてね」
やや厚底の靴を手で取り上げると、|踵《かかと》の部分から小さなチップを取り出した。
「これは ───」
「パスワードは『ガラク』、私の娘の名だ」
コンピュータでデータを開いたクリスは、頬に拳を当てて|唸《うな》った。
「そういうことだ。
総力戦に備えて、お互いに無益な血を流さないための措置だと思って欲しい」
収められていたのは、最後の決戦になったときに基地を捨て、正規軍を切り抜けて再起を図るための飛行ルートと、落ち合うポイント、そして使用する暗号などだった。
「やはり、ナセルも感じているか」
正規軍には、最後まで守り抜く国がある。
だが、外人部隊は寄せ集めの雇われた兵士である。
敵味方に分かれているからと言って、崩壊しようとしている国のために死ぬ理由はない。
まして、ナセルもクリスも旧知の仲である。
「内通を知ってしまった者は、始末されるのが世の常だが ───」
シールドという、ポピュラーな拳銃を腰にピッタリ押し付けたまま、銃口をゼツに向けた。
「まあ、|流石《さすが》にそう来るだろうな」
両手を上げて、目を伏せたゼツはクリスの言葉を待った。
だが何も言わず、銃をホルスターに収めてクリスも窓ガラスの雨粒に視線を移した。
「ホーネットのパイロットだが」
「ああ、私の夫、ラルフのことかい」
雨粒の向こうには、底知れぬ闇が広がっていた。
「奴は、死ぬかもしれないぞ」
ジェナーと肩を並べて談笑して歩くガラクは、|傍目《はため》には友達同士でお喋りを楽しむ若者に見えた。
「へえ、じゃあ軍隊に入ってからまともな訓練も受けずに、ここに来たってわけ」
「そうなの。
銃の扱い方だけはレックスに教わったのだけれど、実戦で敵を撃つには足りないものが、まだまだ|沢山《たくさん》あるわ」
その時、背後に積まれた木箱の山の影から、誰かが近づいてきた。
身を隠すでもなく、堂々として足音を高く響かせながら。
「ライトニングⅡに乗っていた、若い方の女か」
ため息をついて肩をすくめた。
「あなた、盗み聞きしてたのね」
「当たり前だろう、敵の兵士と、こんなに目立つところで話をしていて、何事かと思って聞いていたんだ。
クリストファー・キンバリーだ。
昼間あんたのライトニングⅡに狙いをつけて警告したのは俺さ」
目つきが鋭くて、気後れするほど威圧感があった。
だが顔つきは丸みがあり、幼さが残っている。
「それで、なぜ外人部隊に来たの」
ガラクを2人の視線が射貫いた。
改めて問われると、理由が分からない。
ポカンと口をパクパクしたまま、周囲をキョロキョロと見回すだけだった。
ジェナーはまた、どっと腹を抱えて笑いだした。
「ほら、おもしろいお嬢さんでしょう。
出来の悪いコントみたい」
指を指してゲラゲラ笑う彼女を見て、ガラクも|可笑《おか》しくなった。
そしてキンバリーも口角を引き|攣《つ》らせて、クククッと笑い始めた。
「ここは地獄の激戦区だぜ。
明日をも知れぬエトランゼに、良く分からずに来てしまったみたいな顔してやがるぜ。
本気かよ」
こらえきれなくなって、3人は高らかに声を上げ、天を仰いで大口を開けて笑った。
チェコやスペインのファリーゼ、パリでの出来事がガラクの口を突いて出た。
家を出てから、|怒涛《どとう》のように自分の身に起こった理不尽とも言える運命を、他人に話したのは初めてだった。
ずっと、だれかに聞いてもらいたい気持ちでいっぱいだった。
もしも、戦場以外でこの話をしたら、信用してもらえないかも知れない。
それほど現実離れした運命だった。
突然消息を断った両親と、再会したばかりで、その場所は敵地のど真ん中で、生きているのが不思議だなどと言うと、また笑いが込み上げて肩をゆすった。
キンバリーはガラクと同じ20歳だった。
なのに軍人としては遥かに経験を積んだ先輩だった。
ひとしきり話して、気を許したのか彼が言った。
「実はアル・サドンの兵士がうちの基地でうろついていても手を出すなと命令があったんだ。
敵同士のはずなのに、おかしな話だが、外人部隊の人間は様々な顔を持っている」
「どういうこと」
「例えばお前が入ったガルーサ社から、うちにも派遣されているのさ」
「そうさ、戦争ってやつは色んな顔がある。
影には沢山の陰謀が巡らされていることもある ───」
白髪の小柄な老人が、後ろ手に組んで木箱の上から見下ろしていた。
艦載機乗りとして、アメリカ空軍でも屈指の腕前を誇るケイ・ホワイトは、ハーティ|爺《じい》さんが持って来たスーパートムキャットの性能を確かめながら小隊の前で喋りまくっていた。
「おい、見たか。
アフターバーナーなしで編隊に遅れず付いて行けるぞ」
旧世代の代表格だったトムキャットを改良して、ステルス性能と新型エンジンを搭載したモデルをアメリカが秘密裏に開発していた機体は、途中で放り出されていた。
残っていた設計図を元に、部品をかき集めて試験機を、こしらえて来たのだった。
主翼が大きく開くと、他の機体を圧倒する迫力がある。
この可変翼と、火器管制能力の高さが魅力で、翼の動きから「猫」の耳のようだとか、偵察能力の高さから「ピーピングトム(覗き屋)」のトムなどと言われることもある。
低空飛行するラルフとアリーの小隊を見下ろし、今回も上空制圧をホワイトが任されていた。
「おいでなすったぜ。
今日のエースはどちらか、競争だ、アリー」
ヘルメットの中で軽く舌を出し、唇を湿らせると|操縦桿《そうじゅうかん》を引きながらアフターバーナーに火を入れたラルフは、山なりの軌道を描きながら敵編隊の中心めがけて飛び込んだ。
「ちょっと待て、様子がおかしいぞ」
そこまで言ってアリーは、背筋に悪寒が走った。
何かいつもと違う。
ライトニングや、ハリアーのような小回りが利く機体で構成された敵編隊は、何かを狙っているような予感をさせた。
「一度やり過ごして様子を見ろ、ラルフ」
ホワイトは叫んだ。
「細かいのが揃ったって、乗り手が素人じゃあ話にならんのさ」
耳を貸さずにラルフは正面から突っ込んでいった。
立て続けに発射したミサイルを、小刻みな動きで山間に誘導しながら|躱《かわ》して山服に衝突させてやり過ごす者がいた。
そのまま機影は山の中に消えてしまった。
「ちくしょう、どこへ行きやがった」
「しまった、上だ、ラルフ」
ふわりと大きく浮き上がったハリアーが後方上からバルカン砲の帯をホーネットに浴びせかける。
その時、さらに上方からスーパートムキャットが躍りかかり、敵のコックピットを射貫いた。
滑走路に向かうホーネットのエンジンから、黒い煙が長く伸びる。
待機していた消防車が消火剤を浴びせ、コックピットからラルフを引きずり出した。
頭部に傷を負い、ヘルメットの中に血が溜まっていた。
「へへ、ヘマやっちまったぜ。
バルカン砲の弾が|掠《かす》めやがって、このザマだ。
神様に、チョーシこくなと叱られたな。
ホワイト、恩に着る」
「いいから、もう喋るな」
ストレッチャーに括り付けられた彼は、力なく笑った。
管制塔で椅子に腰かけたまま、ぼんやりとレーダーを眺めていたクリスは無線の音で我に返った。
「ジェナーです、ガラクと共に演習飛行をしたい。
離陸許可を ───」
少し驚いたが、若者同士、そして激しい戦闘に明け暮れる外人部隊では少ない女兵士だ。
多くは聞かなかった。
窓の下に、ハンガーから離れて行くライトニングⅡを認めると、飛行ルートを確認した。
当直の管制官がやって来ても、クリスは持ち場を離れようとしなかった。
「どうか、若い世代が、このアルバラに、|碧空《あおぞら》を取り戻してくれる日が来ることを。
血に|濡《ぬ》れた大地に眠る魂を、|慰《なぐさ》める日が来ることを」
|呟《つぶや》く声に反応して続いた。
「司令、何か言いましたか ───」
レーダーの前を管制官に譲ると、重くなった身体を椅子に沈めて|頬杖《ほおづえ》を突いた。
滑走せずに空へ上がる光を追っていた目に、アフターバーナーの|眩《まばゆ》い|輝《かがや》きが映ると、遥か空の彼方を目指して消えて行った。
そうだ、足踏みしていても兵士たちは死地へと向かって飛んで行く。
続いてキンバリーのクフィルも飛び立った。
「男の尊厳か ───」
いくらか頬がこけて|皺《しわ》を深くした自分の顔も、そろそろ地獄の業火に焼かれる時かもしれない。
パサパサになった髪を掻き上げると、足を引きずるようにして自室へ引き上げて行った。
「ほら、ガラク、演習モードだから思いっきり発射ボタンを押してごらんよ。
キンバリーは、すばしこいからよく狙いをつけて」
拳銃を手にしたときのような、頬のあたりがヒリつく感覚を覚えた。
身体の感覚が消え、「自己」という存在が一つのエネルギーに変わっていく。
照準器の中心に機影を捉えたとき、心に渦巻く違和感が消え、この世界の何もかもが中心に集まってきたようだった。
一発だけ発射したレーザーは、確実にキンバリーのコックピットにヒットした。
そして操縦桿を握ると、ジェナーが言った。
「そう、その調子よ。
あなたには才能があるみたいね。
でも、|溺《おぼ》れちゃだめよ。
良い戦闘機乗りは、自分を持たないものなの。
忘れないでね」
年老いた武器商人が一言、空に向かって呟いた。
「Good Rack ───」
了
この物語はフィクションです
ある日、飼い猫が言葉を話し始めた。猫は、飼い主の知らない秘密を知っていた。
「ご主人様 ───」
妻と2人暮らしの俺は、全身真っ白の猫を飼っていた。
子どもの代わりに、膝の上に載せて一緒にテレビを見たり、散歩をしたり、食事も一緒だった。
そんな猫のサシャが、喋った、ような気がしたのだ。
「ねえ、ご主人様、聞こえてるんでしょう」
サシャはこちらを見つめている。
まさか ───
「ねえ、ご主人様。
私、見ちゃったの」
何か、意味深なことを言った。
「なんだい」
恐る恐る聞き返す。
「奥さんの美奈は、浮気してるわ。
猫は誠実だけど、人間の女はだめね」
俺は、何を言われたのか理解するのに時間がかかった。
幽霊屋敷に住み始めた家族が、奇妙な現象に悩まされる。彼らは、屋敷に隠された秘密を解き明かし、幽霊を成仏させることができるのか?
「幽霊屋敷」と呼ばれる薄気味悪い家だったが、家族が住むには充分な広さだったし、何より家賃が安かった。
少し気味悪いが俺たちはここに居を構えた。
それからというもの、床鳴りに混ざって人の呻き声が聞こえ、鏡の向こうに光の玉が飛んでいたりした。
ある日、トイレの中から女の子のすすり泣きが聞こえた。
ドアを開けると誰もいない。
そして閉めるとまた聞こえるのだ。
さすがに気味が悪くなって念仏を唱えてみることにした。
真言密教に、彷徨う魂を慰める術がある。
見よう見まねで読んでみた。
「オン カカカ ミ サン マ エイ ソワカ‥‥‥」
するとボロボロの服を着た少女が姿を現したのだ。
10年間植物状態だった男が目覚めた。彼は、昏睡中に未来を予知する能力を手に入れていた。
暗い世界に解き放たれた俺は、少しずつ世界が赤くなっていくのを感じていた。
そうだ、俺は目を閉じていたのだ。
少しずつ瞼を開いていく。
あれは夢だったのだろうか。
俺は、廃墟と化した東京を彷徨っていた。
その前に、ここはどこなのだろうか。
「落ち着いて聞いてください」
すぐ近くから声がした。
「あなたは10年間眠っていました。
何か私にできることはありますか」
声は出るのだろうか。
ヒューと気管から音が出た。
仕方がないので、大きく頷いて見せた。
その男は、俺に様々なことを問いかけたが、一つも当たらなかった。
力を何度も込めていると、腕が少し動くようになった。
鏡に映るもう一人の自分が、現実世界に現れるようになった。主人公は、鏡の中の自分と協力し、世界を救う戦いに挑む。
僕の家は山の中の静かな森に囲まれている。
父は、ヨーロッパの家具を好んで揃えたので、家もそれに合う洋館だった。
その中二階に洗面台が据え付けてあり、大きな合わせ鏡がある。
僕が立つと勿論、自分の顔が写るのだが、真夜中の0時になると、鏡の中の自分が喋り始めるのだ。
もう一人の僕は、バーチャル世界からやって来たという。
そして、ある日外の世界に飛び出してきたのだ。
知り合いには、双子の兄弟と言うことにした。
昔からの友人には合わせないようにするしかない。
妹は、突然のことに卒倒しそうになったが、時間をかけて説明した。
もう一人の僕は、どうやら人の心を読み、数秒先の未来を予測する能力を持っているようだった。
その力を使い、世界を混乱に陥れようとしているハッカー集団に立ち向かうために協力して欲しいというのだ。
記憶を売買できる世界で、記憶を失った男が自分の過去を取り戻そうとする。しかし、彼の記憶には、世界の命運を左右する秘密が隠されていた。
俺は一体、何者なのか。
ある部分の記憶がすっかり抜け落ち、子どものころの記憶と最近の記憶が繋がっているような違和感があった。
空白の時期に、何か重大な秘密があるのではないか。
そう思い始めたのは、時々自分を観察する視線を感じるようになってからだ。
この前はカフェに入ったときに、新聞の裏からちらちらとこちらを見ている男がいた。
マンションに帰ってきて、自動ドアを開けた瞬間、路上駐車している黒塗りの車から、窓越しに見られている気がした。
手がかりがないわけではない。
毎朝円周率の計算をする癖があって、スラスラと数千桁まで言えるのである。
なぜこんな特技があるのか、理解できないが恐らく空白の時間に関係しているのだろう。
そう、俺は数学者なのではないか。
何かの暗号を解く鍵を握っているのではないか。
だからつけ狙う奴らがいるのだ。
あるSNSで「いいね」を押すと死ぬという都市伝説が広まる。
そして、その真相を確かめるため、危険な調査に乗り出す。
闇の情報サイト、マッドウエブのアカウントを持つ者は、世界を支配できるとされている。
情報セキュリティが飽和点に達しつつある現在においては、ハッキングなど現実的な技術ではなくなった。
代わって人間の精神を直接支配する方法が取られるようになったのである。
誰もが気軽に使っているSNSにおいて、闇の住人が書き込みをすることもある。
そんなアカウントに「いいね」ボタンを押すと、死が訪れるとされていた。
大手IT企業の社員である緒方は、ある筋からマッドウエブの動きが活発化しているという情報を掴んだ。
SNSの「いいね」ボタンを押すと、個人情報が抜き取られる形跡は掴んだものの、その先のルートまではわからない。
「こりゃあ、」
書き込み自体は分かりにくいようにしてあるが、どうとでも取れるように注意を払って作られたようにも取れる。
いいねボタンをとりあえず押してみた。
調査のためとは言え、背筋を汗がしたたり落ちた。
何かがある。
カーテンを少しだけ開き、目を凝らすと通りに人影があった。
世界中の科学者のもとに、地球外生命体からの招待状が届く。
招待を受け入れた科学者たちは、想像を絶する異世界へと旅立つことにした。
人類は、長きにわたって地球外生命体とコンタクトを取ろうとする。
地球上の奇妙な痕跡をつぶさに研究してきた。
そして、2050年を迎え、宇宙へ手軽に行ける時代が到来したとき、運命のメッセージが届く。
電磁波に乗って、人類が傍受できる形で。
「おい、メールを見たか」
データセンターの小型コンピュータのに届いたメッセージは、地球外生命体からの電波をキャッチした驚きと喜びに湧いていた。
すぐに調査チームが組まれ、小型宇宙船に乗った俺は、宇宙の果てを目指して光速の1000万倍という、人類が実現可能な最高速度で射出された。
目的地についたことをAIが知らせると、窓から空を眺める。
綺羅星が霞のように広がるはずの宇宙が、そこにはなかった。
何かの生物の体内のような、バイオな空間に異形の生物がうごめいている。
俺はレーザー銃を片手に船外に出た。
静かな山奥に、ポツンと佇む一軒の古びた山小屋。
都会の喧騒から逃れてやってきた若者が、この山小屋で数日間寝泊まりして楽しんでいた。
突然見舞われた嵐の夜、激しい雨音と共に、見知らぬ男が山小屋を訪れる。
男はびしょ濡れで、憔悴しきっていた。
拓也は男を招き入れ、暖を取り、食事を共にした。
男は、山で道に迷ってしまったと説明した。
しかし、彼の様子はどこか不自然で、疑念を抱く。
彼は、時折意味深な言葉を呟き、窓の外を不安げに見つめていた。
翌朝、嵐は過ぎ去り、山は静けさを取り戻していた。
2人は共に山を下りることにした。
しかし、山道を歩いている途中、彼は突然立ち止まり、見つめてきた。
「実は…」
自分は未来から来たタイムトラベラーだと告白した。
彼は、未来に起こる大災害を知らせるために、過去に戻ってきたのだという。
そして、その鍵を握るのが、この山にあるという。
半信半疑ながらも、彼と共に山を探索する。
すると、彼らは、古びた祠を発見する。
祠の中には、不思議な光を放つ石があった。
「これだ!」
石に触れると、彼は突然光に包まれた。
そして、次の瞬間、消えてしまったのだった。
一体何が起こったのかわからず立ち尽くしてしまう。
そして石を手に取り、山小屋へと戻った。
数日後、ニュースで驚くべき事実を知る。
未来で起こるはずだった大災害が、未然に防がれたのだ。
未来から来た男の言葉が真実だったことを悟り、彼が未来を変えたことに、安堵と寂しさが入り混じった複雑な感情を抱く。
彼の心には、あの山と、そして未来から来た男との出会いが深く刻まれていた。
時々あの山を思い出し、いつかまた訪れたいと思う。
もしかしたら、そこで再び、未来からの来訪者と出会えるかもしれないと。
都会の喧騒から離れた海辺の町、鎌倉。
古民家を改装したカフェ「汐風」で働く、28歳の barista、藤崎あかりは、穏やかな日々を送っていた。
彼女は、コーヒーを淹れて、お客さんの笑顔を見るのが何よりの喜びだった。
しかし、あかりには少し変わった趣味があった。
それは、「恋の欠片」を集めること。
失恋した人が海に流した手紙、別れた恋人同士が最後に交換したプレゼント、叶わなかった恋の証としてのチケットの半券…
彼女は、海岸を散歩しながら、そんな「恋の欠片」を拾い集めていた。
ある日、あかりは、海岸で一冊の古いノートを見つける。
それは、誰かが書き綴った日記のようだった。
ページをめくると、そこには、切ない恋の物語が綴られていた。
日記の最後には、「このノートを、海に浮かべてください。
そして、私の想いを、誰かに届けてください」
と書かれていた。
あかりは、ノートの持ち主の願いを叶えるため、ノートを海に浮かべる。
すると、不思議なことに、ノートは光に包まれ、空へと消えていった。
数日後、カフェに一人の男性客が訪れる。
彼は、どこか寂しげな表情を浮かべ、窓際の席に座った。
あかりがコーヒーを運ぶと、男性は、彼女を見て驚いたような顔をした。
「もしかして、あなたは…」
男性は、あかりに尋ねた。
彼は、あの日記の持ち主、高木翔太だった。
彼は、ノートが海に浮かべられた後、不思議な夢を見たという。
夢の中で、彼は、あかりに似た女性にノートを渡し、想いを伝えていた。
あかりと翔太は、ノートをきっかけに、心を通わせていく。
二人は、お互いの過去や、今の気持ち、そして、未来への希望を語り合う。
あかりは、翔太との出会いが、ただの偶然ではないように感じた。
それはまるで、彼女が集めた「恋の欠片」が、二人を結びつけたかのようだった。
やがて、あかりと翔太は、惹かれ合っていく。
二人は、海辺でデートをしたり、カフェで一緒にコーヒーを飲んだり、穏やかな時間を過ごす。
そして、ついに、翔太は、あかりに告白する。
あかりは、翔太の言葉に涙を浮かべ、頷いた。
二人は、優しく抱きしめ合った。それは、新しい恋の始まりだった。
あかりは、これからも「恋の欠片」を集め続けるだろう。
それは、彼女にとって、大切な思い出であり、そして、未来への希望でもあるからだ。
そして、いつかまた、誰かの想いが詰まった「恋の欠片」が、誰かの心を癒し、新たな恋を芽生えさせるかもしれない。
都会の喧騒から逃れ、古都鎌倉に移り住んだ写真家、水島陽菜。
彼女は、古い一軒家を改装したアトリエ兼自宅で、静かな日々を送っていた。
陽菜は、光を捉えようとしていた。
対象は風景であったり、人物であったり、時には日常の些細な一瞬であったりする。
そして、陽菜にとっては習慣になっていた。
その習慣は、「記憶の光」を集めることに昇華されていく。
古いカメラを片手に、鎌倉の街を歩き回る。
そして、心惹かれる光を見つけると、シャッターを切る。
それは、古寺の静謐な光、路地裏に差し込む木漏れ日、夕焼けに染まる海、そして、人々の笑顔だった。
彼女は、これらの写真を「記憶の光」と呼び、大切に保管していた。
ある日陽菜は、一枚の不思議な写真を見つける。
それは彼女が撮った覚えのない写真だった。
写真には、見覚えのない女性が、優しい笑みを浮かべてこちらを見つめていた。
写真の女性は、どこか懐かしさを感じさせる雰囲気を持っていた。
陽菜は、この女性が誰なのか、そして、なぜこの写真が自分のカメラに入っているのか、不思議に思った。
数日後陽菜は、カフェで一人の女性客と出会う。
彼女は、あの写真に写っていた女性にそっくりだった。
陽菜は、勇気を出して女性に話しかける。
「あの、もしかして、この写真に写っているのは…」
女性は、写真を見て、驚いたような顔をした。
「これは、私の祖母です。亡くなった祖母が、大切にしていた写真です」
女性は、涙を浮かべながら、陽菜に話してくれた。
彼女の祖母は生前、鎌倉に住んでおり、写真家を目指していたという。
陽菜と女性は、写真をきっかけに、心を通わせていく。
二人は、お互いの過去や、今の気持ち、そして、未来への希望を語り合う。
女性との出会いが、ただの偶然ではないように感じた。
それは、まるで、彼女が集めた「記憶の光」が、二人を結びつけたかのようだった。
やがて、陽菜は、女性から一枚の写真を受け取る。
それは、女性の祖母が最後に撮った写真だった。
写真には、美しい夕焼け空が広がっていた。
陽菜は、その写真を手に取り、鎌倉の海辺へと向かう。
そして、夕焼け空に向かって、シャッターを切る。
その瞬間、彼女は、不思議な感覚に包まれた。
それは、まるで、女性の祖母が、彼女を通して、この美しい瞬間を捉えようとしているかのようだった。
陽菜は、これからも「記憶の光」を集め続けるだろう。
それは、彼女にとって、大切な思い出であり、そして、未来への希望でもあるからだ。
そして、いつかまた、誰かの想いが詰まった「記憶の光」が、誰かの心を癒し、新たな光を灯すかもしれない。
古びた骨董品店「時の砂」を営む、見た目は二十代前半の美しい女性、エリザベート。
しかし、実は数百年の時を生きる吸血鬼だった。
悠久の時の中で、彼女は一つの奇妙な趣味を持つようになっていた。
それは、砂時計を集めること。
彼女にとって、砂時計は有限の時間を象徴する存在だった。
エリザベートは、世界中を旅し、様々な砂時計を収集していた。
砂時計の中に閉じ込められた砂は、彼女にとって、人間たちが無意識に浪費している貴重な時間を表していた。
彼女は、その砂を眺めながら、人間の儚ささと、自身の孤独を噛み締めていた。
ある日、エリザベートは、不思議な砂時計を手に入れる。
それは、砂が落ちる度に時間を巻き戻すことができる砂時計だった。
彼女は、この砂時計を使って、過去の過ちを償いたいと願うようになる。
しかし、過去を改変することは、新たなパラドックスを生み出す可能性がある。
エリザベートは、葛藤しながらも、砂時計を使う決意をする。
過去に戻ったエリザベートは、一人の青年、翔と出会う。
翔は、時計技師を目指しており、時間を大切にする心優しい青年だった。
エリザベートは、翔に惹かれながらも、自身の正体を隠さなければならない苦悩を抱える。
翔もまた、エリザベートに特別な感情を抱くようになる。
しかし、彼は、彼女が何かを隠していることを感じていた。
ある日、翔は、エリザベートの秘密を知ってしまう。
彼は、彼女が吸血鬼であること、そして、過去を改変しようとしていることを知る。
翔は、驚きと恐怖を感じながらも、エリザベートへの想いは変わらなかった。
エリザベートは、翔に全てを打ち明け、過去を改変する計画を話す。
翔は、彼女の計画に反対するが、エリザベートの決意は固かった。
エリザベートは、砂時計を使い、過去を改変する。
しかし、それは、彼女が望んだ結果をもたらさなかった。
過去を変えたことで、新たな悲劇が生まれてしまったのだ。
エリザベートは、自分の愚かさを悔やみ、絶望する。
しかし、翔は、そんな彼女を優しく抱きしめる。
「エリザベート、過去は変えられないかもしれない。
でも、未来は変えられる。
僕と一緒に、新しい未来を歩もう」
エリザベートは、翔の言葉に救われ、再び生きる希望を見出す。
彼女は、砂時計を捨て、翔と共に、未来へと歩み始める。
二人の前には、どんな未来が待ち受けているのだろうか。
それは、誰にも分からない。
しかし、彼らは、共に支え合いながら、未来を切り開いていくことだろう。
広大な空に無数の星が瞬く、魔法と科学が共存する世界、アストレア。 この世界では、人々は生まれた時に「星のかけら」を授かる。
それは、一人ひとりの魂の一部と言われていた。
ルナは17歳の少女である。
彼女は幼い頃、兄のレオンと「星のかけら」を交換し合った。
しかし、ある日レオンは行方不明になり、ルナには兄の残した「星のかけら」を手に取った。
数日後、ルナは兄の「星のかけら」が微かに光り出すのを目撃する。
それは、レオンがまだ生きている証。ルナは兄を探す決意を固め、旅に出た。
彼女の手には、兄の形見と、世界地図が記された古びた手帳。
旅の途中、ルナは様々な人々と出会う。そして、彼らの「星のかけら」が持つ輝きに触れる中で、兄の「星のかけら」に共鳴する欠片を探すようになる。
それは、兄の足跡を辿る手がかりであり、兄の魂の一部を繋ぎ止める希望でもあった。
しかし、旅は順風満帆とはいかない。ルナは、深い森に住む魔物や、魔法使いに襲われる。
それでも、彼女は決して諦めなかった。
兄への強い想いと、道中で出会った人々との絆が、彼女を支えた。
旅の終わり、ルナはついにレオンを見つける。
しかし、彼は記憶を失っていた。
そして、彼の「星のかけら」は、ルナの持つ欠片とは全く異なる輝きを放っていた。
ルナは、絶望する。
しかし、その時、古びた手帳に記された最後のページが目に入る。
そこには、驚くべき真実が書かれていた。
レオンは、実は、世界を滅ぼそうとする「闇の魔術師」だった。
そして、ルナが探し求めていた「星のかけら」は、闇の魔術師の力を封印するための鍵だったのだ。
ルナは、愛する兄と世界の平和、どちらを選ぶのか迫られる。それは、残酷な選択だった。
しかし、ルナは決断する。
彼女は、兄の「星のかけら」を自身の欠片と合わせ、闇の魔術師の力を封印する。
そして、レオンは、再び記憶を失い、穏やかな表情で眠りについた。
ルナは、兄の眠る場所を見つめながら、涙を流す。
彼女は、兄との再会を喜びながらも、兄が犯した罪を許すことができない。
しかし、ルナは、前を向くことを決意する。
彼女は、兄の「星のかけら」を大切に保管し、再び世界を旅する。
今度は、人々の「星のかけら」の輝きを集め、世界に平和をもたらすために。
前作で「焼き魚食道」を大成功させた文月は、いくつかの案件を片付けた後地域のコミュニティ改革に参加していた。そんなある日、突然の来客から依頼を受けた。相手は経営が苦しい、地域の百貨店だった。東京の老舗百貨店でさえも、支店を閉店しているという。正直なところ百貨店など時代遅れだと思っていた文月だが、一度クライアントになれば全身全霊で調査を始める。そして必ず勝たねばならない。彼が今回目をつけたのは、なんと ───
「本日はご来店いただき、まことにありがとうございます」
ショーウインドウでは初夏の爽やかなアズールブルーに彩られた背景に、マネキンが躍動的なポーズを取る。
正面玄関のガラスドアにステンレスの肉厚の湧くが煌めく。
買い物客の笑い声とともに、中へと吸い込まれていく流れが止むことはない。
夫人物の小物やネックレスのガラスケースの向こうから、きちんと両手を揃えて頭を下げる女性店員には気品があった。
入口の特設コーナーに、夏用の帽子が並び季節感を出している。
客の群れはエスカレーターに向けてほとんどが流れ、一部エレベーターの方へと向かう。
人の流れも滞りがない。
キョロキョロと辺りを見回しながら、|瑞樹《みずき》 るりはスマホに何かを打ち込んでいる。
黑い帽子を|目深《まぶか》に|被《かぶ》り、上下共に黒いフォーマルな印象のシャツとパンツ。
化粧品売り場では、カウンターにあるおびただしい量のテスターが並び客がカウンターの前の椅子に腰かけて店員と談笑している。
巨大なポスターが並び、強い照明で金属やガラスの光沢感を際立たせる演出をする。
百貨店は、長年|培《つちか》ったノウハウがある。
注意深く観察していれば、洗練されたデザインと販売促進のコツを見いだすことができた。
ハンドバッグが並んだ一角に、白髪交じりの男が立っている。
落ち着いた|佇《たたず》まいだが、周囲の様子を伺いながら店員に指示を出しているようだ。
瑞樹は革製のショルダーバッグから名刺を取り出して、男に差し出した。
「コンサルタントの瑞樹さんですね。
お噂は近隣の商店街に広がっていますよ」
口角を上げて目尻を下げ、満面の笑みを作った男は|青山 翔太《あおやま しょうた》と名乗り、販売促進部長と名刺に書かれていた。
もう一人、40歳くらいの女性が着いてきた。
こちらは|秋山 美咲《あきやま みさき》と言い、同じく販売促進部の社員だった。
化粧とスーツの着こなしは、瑞樹が引け目を感じるほど身ぎれいに整えている。
青山部長は屈託なく笑い、気さくな話し方をするが、立ち居振る舞いに一分の|隙《すき》もない。
まだ29歳の瑞樹は、早くも雰囲気に飲まれかけていた。
手狭なオフィスの机には、うず高く積まれた本が並び、窓からの光とデスクライトで照らされた男が眉間に|皺《しわ》を寄せて、次々にページをめくる。
「戻りました」
少々疲れた声を出した瑞樹が、隣りのデスクにバッグを置くと、椅子にストンと腰を落とした。
「ああ、で、どんな話だった」
本から目を離さずに|文月 優斗《ふづき ゆうと》が聞いた。
「どうもこうも、百貨店は完成されたデザインで固められていて、私が指導することなんて、ないと思うのだけど ───」
小さくため息を吐いて、横目で文月の様子を|窺《うかが》っていたが、やれやれといった風に肩をすくめた。
「君よりも年配の販売促進部に指導するのだから、それなりの準備がいるはずだ」
「文月さん、もう何か仕込んでいるのでしょう。
黒ずくめの服装で行ったのは、何のためなんです」
少々|苛立《いらだ》った声を出した。
ようやく本から視線を上げて、瑞樹の方に向き直った彼の顔には、鋭い眼差しと引き結んだ口元が緊張感を|醸《かも》し出している。
「俺は、今回最初から勘違いをしていた。
百貨店は地域のリソースとして、優れた存在だった。
小手先の技術はまったく通用しないだろうな」
息を飲んだ瑞樹の顔にも、緊張が移ったようだった。
クライアントの方が、用意周到に依頼内容を精査して資料を大量に示してきた。
本来こちらの仕事だが、先手を取られてすでに負けた気分になって帰ったのだった。
「SDGsがキーワードだろう」
ズバリと言い当てられて、次の言葉が出なかった。
今回の依頼主である、セレスト・パレ・ミナミ百貨店は、埼玉県南区デジタルタウンの中心に位置する。
人の流れが良い繁華街にあり、表向きは|賑《にぎ》わっていた。
そして、内陸部のため夏の猛暑でも有名である。
屋上でビアガーデンを開いていたが、最近は客足が減ってやめていた。
ところどころに|綻《ほころび》があるはずだが、それを補って余りあるほどの|煌《きら》めく演出と賑わいがあった。
瑞樹はもう一つため息をついて、ワープロを打ち始めた。
セレスト百貨店の前には、スレートの歩道が観光地へと伸びている。
反対側には駅があり、近づくほどに人混みが|増《ま》していく。
商店街をざっと見たところ飲食店や格安を武器にしたチェーン店が多く、専門店が少ない。
いくつか看板や店の外装を写真に収め、スケッチをしてから一息つくように、セレストのベンチに腰かけた。
文月から送られてきたデータを、スマホで開いて見ていた女は20代半ばだろうか。
そこへ瑞樹が額の汗をハンカチで慎重に拭いながらやってきた。
「|神楽 椿《かぐら つばき》さん ───」
呼ばれて弾かれたように立ち上がると、スマホをビジネスバッグに放り込んだ。
2人とも文月の指示で黒いフォーマルで引き締まったいで立ちに、ベレー帽を目深に被っていた。
足元から頭まで、視線でゆっくりとなぞる瑞樹は、またため息をつく。
「若い人が着るとフォーマルもいいなって思いますね」
「文月さんに考えがあってのことだと思います。
でも、なぜ全身黒なのでしょう」
瑞樹の方が聞きたいくらいだが、年下のデザイナーに聞かれると同調もできなかった。
神楽は美大を出て数年しかたっていない、駆け出しのデザイナーで今回の案件のパートナーとして、他の事務所から文月が指名したのだった。
「きっと、今回の戦略の|要《かなめ》になっていると思います。
恐らくターゲットがビジネスマンなのでは ───」
自分の口から出た言葉に、瑞樹は|雷《いかづち》に打たれた。
目を見開いて、口を開けたまま脳に広がる世界をセレストの人混みに重ねた。
そうだ、よく見てみれば休日にカジュアルな服装をしているのは当たり前だった。
子ども連れが少なくて、同年代の同性、お年寄りと中年、そして独りで来る顧客が多い。
百貨店と言えば子ども向けのイベントを開いて親を|釣《つ》るものだと思い込んでいた。
「リサーチの第一段階は、入口に立って観察することです」
指し示した方を見て、神楽が|唸《うな》った。
「お客さんが、たくさん来ていて経営に困っている感じはしませんね ───」
「想像してください。
この方たちが、普段どんな暮らしをしているかを」
身を乗り出して、眺めていた神楽は、困ったように肩をすくめて見せた。
「リサーチって、難しいですね」
事務所へ戻った2人は、写真やリサーチしたデータを入力して一息ついた。
「それにしても、コンサルを専門にされてる方の分析力は|凄《すご》いです。
私はまだまだで ───」
神楽は瑞樹の4つ下だが、童顔で高校生のようなあどけなさがあった。
ブラインドの|隙間《すきま》から夕日が規則的な筋を落とし、空気が少しひんやりとして来ていた。
自分より経験が浅いデザイナーと共に行動することで、瑞樹の脳裏にあった もやもやが晴れつつあった。
隣りにいなくても、|掌《てのひら》で転がすように思考の|綾《あや》を解きほぐしていく。
同じ土俵で戦い続け、負け続けている辛さに飲まれかけていた自分の心情を理解して、絶妙なパートナーを選んでくれた。
だが、分かっているからこそ従えない。
自分の意地を通したい気持ちが、背後で|陽炎《かげろう》のように黒い炎となって ゆらめくのを感じた。
「それで、SDGsに関連したイベントを企画して欲しい、というのが今回のメインの仕事ですよね」
「率直に、どんなイメージ持った」
瑞樹は鋭い視線を向けた。
「2030年を目標に、持続可能な社会を作る良い行いリストですか」
「ちょっと違うわ。
将来の世代を意識することによって、企業の利益を産みだす取り組みと言った方が今回の案件には合うんじゃないかしら」
|頬杖《ほおづえ》を突いた神楽の|眉間《みけん》に|縦皺《たてじわ》が刻まれる。
2人とも、しばらく唸ってはパソコンで何かを調べていた。
ふと、文月の机に視線をやると、書置きがあった。
「今日は直帰します。
明日、別の件でセレストへ行くので、|進捗《しんちょく》報告を一緒にしてください。 文月」
今日の明日で報告するのか、とため息をついた所で神楽が立ち上がった。
「リサイクル商品を提案するとか、お客さんが増えるようなクーポンとかセールとか作りましょうか」
違和感を隠せない瑞樹の表情に、神楽も少し|怯《ひる》んだが決然とした覚悟を眼差しに秘めていた。
「そうね、まずは具体的な提案が必要でしょうね」
|曖昧《あいまい》な返事をして、残りの仕事は各自家に持ち帰ることにした。
翌日、文月も黒いジャケットに黒スラックス、黒シャツでカンカン帽といういで立ちである。
3人がセレストのロビーで手持無沙汰に待っていると、買い物客が好奇の目を向けてきた。
「何かのコスプレだと思われてるんじゃないかしら ───」
「もう、なんでこのファッションなんですか」
苛々を爆発させた瑞樹は、ついに文月に詰め寄った。
「君も、大体理解していると思うのだけどなあ ───」
あさっての方向を見ながら、手のひらを返して|大袈裟《おおげさ》に肩をすくめたポーズが、妙に似合っていて次の言葉が出なかった。
「まあまあ、楽しんでいきましょうよ」
神楽は足を組んで腰に手をやり、床に視線をやって不可解なポーズを取る。
まるで3体のマネキンが身を|捩《よじ》っているように、近付き|難《がた》いムードを|醸《かも》し出していた。
「ああ、文月さん。
瑞樹さんも、お世話になります」
先日の青山部長が奥へと促した。
通用口を入り、会議室へ入ると文月が切り出した。
「セレスト様の成長戦略を考えてきました。
その前に、瑞樹から報告があります」
目くばせを受けて、バッグからタブレットを取り出した瑞樹は、テーブルの端に置いて話し始めた。
「名付けて『氷のメッセージ ~ 人影が語り掛ける未来 ~ 』です。
氷屋さんの低温でじっくり作った|純氷《じゅんぴょう》を人型に並べます。
もう一つは黒い紙の上で同じように人型を作るのです。
人間が生きていくためには、氷が自然な状況に保たれなくてはならない。
つまり、地球温暖化に対するメッセージが込められているのです
いかがですか、この企画で注目度爆上がりですよ」
言い切った瑞樹は、糸が切れた操り人形のように椅子にストンと落ちた。
青山部長は、ポカンと口を開けたまま液晶画面を見つめている。
神楽は、不意打ちでも食らったように目を見開き、瑞樹の横顔を凝視したままである。
|顎《あご》に|拳《こぶし》を当てたまま、|瞑目《めいもく》していた文月は静かに目を開けた。
瑞樹が唾を飲み込む音が、神楽の鼓膜を揺らした。
「これで、大丈夫ですか」
おずおずと青山が声を絞り出す。
机に視線を落とし、また瞑目した文月はコクリと|頷《うなづ》いた。
イベントの打ち合わせのために、セレストの屋上へやってきた瑞樹はだだっ広い空間を横切ってフェンス際までやってきた。
後について、青山部長と神楽が周囲を値踏みするように見回しながら歩く。
「け、結構広いのですね ───」
数年前まで、バブル期を思わせるような屋上遊園地を営業していた場所は、跡形もなく片付けられて、コンクリートを空色に塗装した床面があるのみだった。
中央に白い台を2つ設置して、同じ氷人形を1|対《つい》設置する。
撮影する方向や、コンテンツの配信方法を検討して準備に取り掛かる。
まずは氷制作ドキュメンタリーとして、天然の氷を切り出しおがくずにくるんで保存するところ、それを|繋《つな》ぎ合わせて彫刻する映像が制作された。
これは「予告編」として動画配信サイトから放送された。
同時にSNSでも写真とエッセイが|綴《つづ》られた。
神楽のインフィード広告によって、瑞樹のストーリーが映像化され、期間を区切って氷の出来栄えを追いかけていく。
そしてイベント当日を迎えた。
「瑞樹さん、本当に大丈夫でしょうか。
私、足が震えてます」
黒一色の神楽は、腰が抜けたように椅子に座ったきり立てなくなった。
「もう、文月もあなたも信用してないのでしょう。
ここまで来たら、デンと構えなさいよ」
少々苛立った声でたしなめたとき、2つの木箱が到着した。
等身大のアイスボックスなどないので、|梱包材《こんぽうざい》の専門業者に特注で作らせたものだった。
改めて見ると、立派な箱に自分の思い付きが塊になって収まっていることが|滑稽《こっけい》にさえ思えた。
「やっぱり、この日がきちゃったのね」
ボソリと|呟《つぶや》いた瑞樹は、箱に近づくと封を解いた。
あっという間に梱包材が取り除かれ、氷が姿を現した。
「MRIとか、何千万もする医療機器を運ぶ時の梱包と同じなんだってさ ───」
あまりのスケールに面食らうばかりの神楽には、うわごとのように頼りなく聞こえた。
片方には黒い紙が半分貼り付けられていた。
誰も声を出さず、|淡々《たんたん》とスタッフが設置する模様もライブ配信された。
|最早《もはや》、現実味のない光景がスマホの画面にも映し出されていたのだった。
黑い氷人形の台座に「|黒曜《こくよう》」と名前が大きな書道文字でダイナミックに書かれている。
そして対する「|氷雨《ひさめ》」は静かな筆致で煌めく銀の線が透明感を引き立てる。
2体の人形は、瑞樹と神楽のようにも見えた。
きっと黒い方が瑞樹だろう。
氷雨は晴天の陽射しを全身に通し、宝石のように|煌《きら》めいていた。
黒曜は熱をたっぷりと含んだ光を受け止め、身体の中に取り込んでいく。
早くも汗をかき始めていた。
神楽のような経験の浅いデザイナーに対して、正面から向き合えない自分。
競争意識ばかりを持ってしまうのは、自信のなさの表れ。
分かってはいるが、内に|籠《こも》るエネルギーが、黒い|焔《ほむら》となってゆらぎ立ち上る。
「私、ちょっと気分が悪くなったからコーヒーでも飲んで来るわ」
ずっと見守っている必要はない。
氷がただ溶けていくだけだ。
どうしても、自分の行く末に思いが至る。
きっと才能がないのだろう。
その時、スラリとした男が傘を差して歩いてきた。
黒いジャケットに黒いパンツ。
そして黒のベレー帽は瑞樹とお|揃《そろ》いだった。
「どこへ行くんだ。
これから奇跡が起きるというのに ───」
何も言わずにすれ違い、通り過ぎていった彼女の脳に、ある言葉の残響が染み渡る。
「奇跡 ───」
男は顔だけ横を向けて、天井を仰ぎながら言った。
「宇宙から、奇跡の|漆黒《しっこく》が ───」
瑞樹は口角を上げた。
「焔立つ氷に奇跡が ───」
そう、その男は超えられない壁、文月 優斗だった。
「さあ、面白いショーが始まるぞ。
気分も晴れてくるだろうさ」
文月が伸ばした左手に、瑞樹の指先が触れた。
「うん」
2人は手を携えて、神楽の元へと戻って行った。
デジタルタウンの|老舗《しにせ》百貨店である、セレストのイベントは、それなりに認知されていた。
駅近くのカフェには、若者がスマホを片手にドリンクを飲みながら談笑している。
「あの氷、どれくらい持つかな」
「5、6時間が良いところだって書いてあるわよ」
ノートパソコンを広げて、キーを叩いていた|上田 拓也《うえだ たくや》は、BGMを楽しむかのように若者たちの喧騒を、聞くとはなしに聞いていた。
「セレストの氷、話題になっているな ───」
気に留めてはいたが、ローカルニュースだと軽視していた。
周囲を見渡すと、スマホに釘付けになっている者が多いことに気づいた。
ライブ中継が始まったはずである。
SNSを確認すると、氷が溶け始めたとか、水が溜まり始めたとか逐一大量の書き込みが上がっていた。
「ねえ、日傘持ってきた」
「ないよ、男が持つ物じゃないし」
「私の、一本貸してあげるから行ってみようよ」
隣りの男女が立ち上がって、急いで|支度《したく》をし始めた。
他の席でも、傘を手に出て行く者がいる。
上田はもう一度視線を上げ、外の強烈な陽射しに目を細めた。
何かが起こっている。
街全体を騒がせる、何かが。
直観した彼は、残りのアイスコーヒーを喉に流し込み、身支度を整えると外へ出て行った。
繁華街の中心部にあるセレストの入口には若者たちの姿があった。
カフェと同じようにスマホを片手に壁に寄りかかったり、何人かで輪になったりして何かを共有しようとしていた。 エスカレーターで人の流れに乗って屋上を目指すと、途中で売り場へと消えていく客が少ない。
みんな同じところを目指しているようだった。
広いオープンスペースにすっかり様変わりした屋上には、人垣ができていた。
そして、誰もが日傘を差して中心の方を向きながら手元のスマホを見ているのだ。
わあっと、歓声の波が起こり、どよめきに変わる。
大きな|雫《しずく》が黒い氷の方で落ちたらしい。
悲鳴のような奇声を上げる者もいる。
「おいおい、これじゃあ黒曜が持たないぞ」
隣りの男が|呟《つぶや》いた。
人垣を掻き分けて、上田は果敢に騒ぎの中心へと入っていく。
人の熱気が、じっとりと濡れた肌をさらに汗で湿らせた。
「何だ、あれは ───」
黒曜の傍らには、黒づくめのスーツ姿の男女が立ち、日傘を氷の方へと差し出していた。
少しだけ間を空けて日傘を差した人々が取り囲む。
中には普通の雨傘や透明なビニール傘の者もいるが、誰もが傘を持ち寄って氷の様子を見守っていた。
氷は周囲の熱を奪いながら、自らが崩壊していく。
まるで、人間が崩壊、衰退へと向かう無常の傾向に支配されているように。
「限りある命を、守ろうとする営みが心を打つのか ───」
上田はパソコンに向かい、デパートの屋上で繰り広げられた、奇跡のようなできごとを言葉でまとめようと苦悩していた。
ライブ中継の瞬間視聴者数は、記録的な数字だった。
関連したSNSでの盛り上がり。
氷が大粒の汗をかくたびに、ネットで大量の書き込みがある。
そして人が大挙して押し寄せ、傘を持ち寄った。
ため息とともに書いた記事は、夕方のトップニュースに|躍《おど》り出たのだった。
「お疲れさん」
汗でぐっしょりな帽子を取ると、髪がべっとりと顔に張り付いた。
「ふふ、|酷《ひど》い有様ね」
氷の冷気で多少涼んだとはいえ、直射日光が降り注ぐ屋上は|尋常《じんじょう》ではない。
「でも、いい気分よね」
セレストの青山部長は「こんなに若い人が集まったことは、記憶にないほどだ」と目を丸くしていた。
当の文月は、口数少なく頷くばかりである。
「ねえ、こうなることは、分かっていたのでしょう」
なおも瑞樹が問いただす。
サーキュレーターの前で風に当たりながら、気分が落ち着いてきたのか文月が口を開いた。
「いいや。
今回は瑞樹にも、セレストにも一本取られたよ」
小首をかしげて、瑞樹は少し考えこんだ。
「予想以上だったってこと」
「予想以上なんてもんじゃない。
勉強させてもらったよ。
俺は、無作為の効果は知っていた。
だが、人を動かすのは人なのだと教えられた ───」
視線が瑞樹の方に向けられた。
その視線を避けるように、窓の外を見ると、
「私は、逃げようとしていたの。
自信がなくて、仕事と正面から向き合えなかった。
成功したのは、文月の後押しがあったからだし ───」
夕日がブラインドから差し込む。
そろそろ上がろうかと、瑞樹は腰を浮かした。
「陽は落ちるが、明日になればまた昇る。
同じ一日は二度とこないのだ。
こんなに惜しい夕日は初めて見るかもしれない ───」
帰路についた2人は、その夜泥のように眠ったのだった。
了
この物語はフィクションです